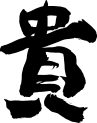朝日新聞 / 田崎真也氏との対談 /
Dec 31, 2019

「日本酒も
テロワールに行き着く」
田崎真也さんの予言
ワインを語るとき、「テロワール」という言葉をよく聞きます。気候や地形、土壌といった「その土地らしさ」を備えているという意味があります。ソムリエの田崎真也さん(61)は、日本酒の原料になる酒米も「ブドウのように個性が表現できる」と断言します。「貴(たか)」(山口県)で知られる若手杜氏(とうじ)の永山貴博さん(44)と磨く、酒造りの本質とは。
永山 蔵の近くに、自社栽培の水田が3ヘクタールあります。10ヘクタールまで増やそうと考えていて、今年コンバインとトラクター、大型のもみすり乾燥機を買いました。
田崎 いま、山口県産米の割合はどのくらい?
永山 80%くらいですが、最終的には100%にしたいですね。
田崎 現在、日本酒の産地表示の制度は米の産地はどこでもよくて、そこの水を使って醸造していれば産地を名乗ることができます。兵庫の米を使っても、山口で仕込めば「山口の酒」とうたえるわけです。
永山 東京や大阪にはない、山口だから味わえる「らしさ」や、土地に息づいた伝統文化は貴重な財産になります。だからこそ、私たちはその本質を大事にしなきゃいけないし、その追求こそが最終的に「テロワール」への尊敬になるんだと思います。田崎さん、どう思われますか。
田崎 業界でも思い始めていますよね。でも日本のラベル表示に関する規定が十分でないので、うまく伝えるすべがない。山口の酒は何が違うのかを表現したいのに、ツールがない。本来ならば地域のテロワールの特徴の違いで産地を細かく分けるべきです。例えば山口県酒造組合のホームページでは8地域に分けていますが、もっと細かくてもいい。中央に山があり秋吉台があり、日本海側、瀬戸内海側で気候も水質も全然違いますからね。
永山 私の父の時代は、アルコール添加や活性炭素で酒の味をバンバン矯正して、常温で保存していました。これでは日本酒はダメになるというギリギリの時期にバトンを頂き、醸造設備や保管環境を整えようとがむしゃらに来ました。
田崎 20年くらい前は「瓶詰め前に試飲しているのか」っていうまずい酒がたくさんありました。でもいま、技術が進化して、そういう酒はないですよね。いい機械や醸造設備が生まれて、世界中で結構うまい「SAKE」ができている。その中で日本酒がどう差別化していくべきか、考えていかないといけませんよね。
永山 醸造技術が高くなり、いいものができるようになった。次はもっと日本酒の本質に目を向けるときなのかな、とも思います。
田崎 欧州のワインで考えれば、ブドウの原産地呼称は、その土地にしかできない味を表示に込めることです。それが町おこしにもなっているんですよ。
酒米でいえば、兵庫の特A地区の山田錦が一番いいのではなく、お米もブドウのようにそれぞれ違った個性が表現できると思うんです。農家の人たちと米作りを一生懸命考えて、その土地ならではの米をつくって、土地の水と気候で得た環境によってできる酒です。日本酒を中心に多くの人が参加できる「6次産業」が完成すれば地域が活気づく。土地の個性を最大限表現しているのが、そこで生まれる酒の頂点です。だから日本酒もテロワールということを考えなければいけないのでしょう。
永山 造り手は売り方を考えるよりも、まず自分自身のものづくりの焦点が絞れていて、多くの人がそれを見たいと思える輝きをつくらないといけない。自分の考えがきちんと収斂(しゅうれん)して輝いていることが重要なのかなと思います。
田崎 造っている人たちは「今年すごくいい酒ができた」と思ったら、「来年はどうやったらもっといい酒ができるだろうか」と考える。「もっといい酒って何だろう」と考え続けることで進化できるんです。どこに行き着くかはそれぞれですが、個性になる。自分の酒を突き詰めることが重要で、その結果、テロワールに行き着くと思うんです。山口はその見本となりえる地域だと思います。
田崎真也(たさきしんや)さん
1958年生まれ。日本ソムリエ協会長。95年、日本人初のソムリエ世界一に。2017年、日本酒の知識や技量向上をめざす認定制度「酒ディプロマ」を始める。
永山貴博(ながやまたかひろ)
1975年生まれ。永山本家酒造場(山口県宇部市)の社長兼杜氏。代表銘柄は「貴」。若手醸造家が蔵を越えて技術向上をめざす「青年醸友会」を立ち上げた。